量子コンピューティング:オープンソースコミュニティが挑む独自の課題(前編)
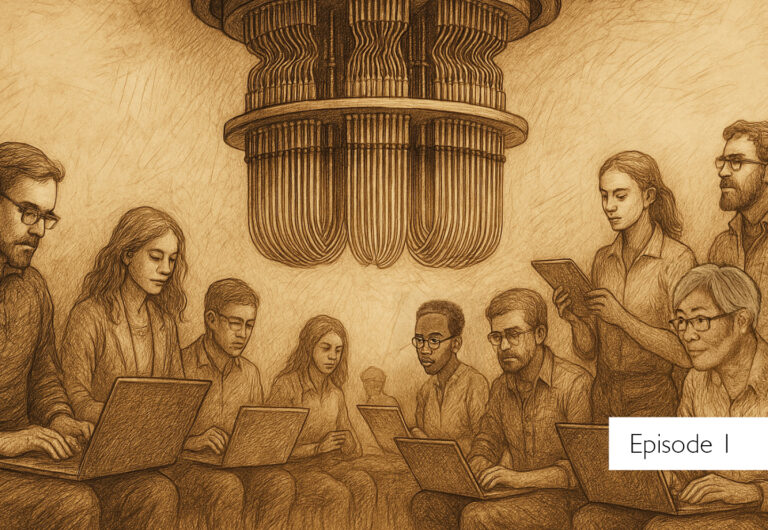
オープンソース量子コンピューティング・コミュニティの構築に挑む
自由かつオープンソースソフトウェアを中心にコミュニティを築くことの難しさは、多くの書籍や記事で取り上げられてきました。本稿で量子コンピューティングを題材に選んだのは、オープンソースプロジェクトがこの分野で特に高い障壁に直面するからです。量子コンピューティングには高度な物理学の知識が必要であり、アルゴリズムを設計しコード化できる人材は極めて限られています。
量子コンピューティングのコミュニティは世界中に散らばっており、この記事の中でもさまざまな地域が登場します。さらに、この分野の研究者は非常に流動的です。たとえば、日本人研究者に加え、欧米から日本にポスドクとして訪れ、一定期間滞在する研究者もいます。
そして、この分野の盛り上がりと期待感から、アルゴリズムを実装できる人材は引く手あまたの状況です。
こうした「小規模だが成長し、国際的につながったコミュニティ」という特徴は、多くのプロジェクトが初期段階で共有するものです。(もっとも、Classiq社のアミール・ナヴェーによれば、量子コンピューティングは自然言語でアルゴリズムを記述できる段階に進化しつつあり、シミュレータの存在によって一般のプログラマーにもコードを書く道が開かれてきています。)
本記事は2回シリーズの第1回で、活発に活動する3つのオープンソースプロジェクトのリーダーたちにインタビューし、コミュニティをどのように構築・維持しているのかを探ります。第1回では Classiq と OQTOPUS を取り上げ、第2回では QuTiP を扱い、最後に総括を行います。
Classiq
GitHubの説明によれば、Classiqライブラリは量子アルゴリズムとアプリケーションの最大規模のコレクションです。Classiq社が立ち上げ、MITライセンスで公開されたこのライブラリには、世界中から200名以上のコントリビューターが参加しています。
私は、Classiq社の共同創業者でCPO(最高製品責任者)、そして量子アルゴリズム責任者でもあるアミール・ナヴェーに、このコミュニティをどのように構築したのかを聞きました。
会社と戦略
Classiq社は量子コンピューティング向けのコンパイラとIDEを開発しています。現在、IBMやIQMといった約10の量子コンピューティングプラットフォーム、さらにIntelやNVIDIAなど4つのシミュレータプラットフォームをサポートしています。ナヴェーによれば、Classiqは量子ソフトウェアに特化した企業として世界最大規模で、従業員は約70名、来年には120名まで拡大する計画です。最近のベンチャー投資により1億7千万ドルを調達し、20社以上のエンタープライズ顧客を抱えており、その多くは量子コンピューティング分野の先進ユーザーです。
同社のビジネス戦略は、いわゆる「クローズド・コア」型です。コンパイラとIDEといったコア製品はプロプライエタリ(非公開)ですが、オープンソースのツールとアルゴリズムライブラリを充実させることで、自社のコンパイラ市場を広げ、高品質なブランドイメージと顧客との強固な関係を築いています。
特にナヴェーは、金融、製薬、物流、サイバーセキュリティといった各業界向けのアプリケーション群を備えた成熟したソリューションを持ち、顧客との協業を通じて構築していると述べています。研究者や学術機関もClassiqのツールを利用しています。すべてを一社で賄うことは不可能であり、オープンソースであることによって顧客ニーズに応えることができるのです。ライブラリはプラットフォーム非依存で、コンパイラが対応するあらゆるハードウェア上で動作します。
開発者層の拡大
Classiqは創業当初から、オープンソースライブラリへのコントリビューター獲得に多大な努力を注ぎました。同社はテルアビブに本社を置いていますが、初期の貢献は南アジアからが多かったとナヴェーは語ります。北米やヨーロッパからの貢献者を増やすため、Classiqは量子分野で有力な大学130以上を調査し、戦略的に関連する研究者に働きかけました。
最初の1年間、同社は水準に満たない貢献も積極的に受け入れ、貢献者と密接に協力して品質を高めました。現在2年目に入り、同社はより選択的になり、要求に合わない貢献は拒否できる段階になっています。
このようにコミュニティ形成に戦略的に注力することで、Classiqは事業計画を遂行しつつ、世界に役立つ大規模オープンソースプロジェクトを育成してきました。同社はスタッフを通じて各貢献を承認する仕組みを設け、プロジェクトに対する強固な管理を維持しています。
OQTOPUS
OQTOPUSは大阪大学が立ち上げた包括的ソフトウェアプラットフォームです。私は、大阪大学量子情報・量子生命研究センターのソフトウェアエンジニア兼研究者である宮永崇史氏にEメールで話を聞き、GitHubを通じて多様な組織から貢献を得るこのプロジェクトのコミュニティ形成について伺いました。
協調的な出発点
宮永氏によれば、このプロジェクトは「日本で初期に開発された複数の超伝導量子コンピュータ用クラウドソフトウェアスタックを統合しようとする取り組みから生まれた」といいます。大阪大学は2023年に独自のプロジェクトを進める一方、富士通でも別の量子プロジェクトを構築していました。大学は理化学研究所(基礎科学と応用科学の両面における日本最大級かつ最も包括的な研究機関)とも協力し、これら3つのプロジェクトを統合して2024年9月にOQTOPUSを発表、2025年3月にApache License 2.0の下で公式リリースしました。
さらに東京を拠点とするTIS株式会社や株式会社セックといった産業界のパートナーも参加しています。
オープンソース化を選んだ理由について宮永氏は、多くのフリーソフトウェアプロジェクトと共通する動機を挙げています。すなわち「利用の障壁を下げ、開発を加速し、世界的な人材パイプラインを形成する」というものです。さらに「大阪大学はアーキテクチャ、開発、運用、コミュニティ調整に深く関わっている」とも述べています。
しかし筆者は、それ以上の理由もあると考えます。もしOQTOPUSがプロプライエタリであったなら、誰が所有するのでしょうか? 大阪大学や理研がそこから利益を得るのでしょうか? 富士通が管理することになるのでしょうか? 多くの人や組織が関心を寄せるソフトウェアは、自然に「共有財産(コモンズ)」であるべきなのです。
現在、富士通・大阪大学・理研は大規模な量子システム共同研究に参加しています。
コミュニティ参加と資金調達
OQTOPUSは大阪大学の「量子ソフトウェア研究拠点(QSRH)」を通じて積極的にメンバーを募集し、研究活動に新たな貢献者を迎えています。QSRHは大学により任命された教授が調整するコンソーシアムであり、「パートナー組織は共同研究のためにメンバーを派遣し、それぞれの研究者や技術者が特定の技術分野を担当する」と宮永氏は説明します。
資金は大阪大学や研究開発契約から拠出され、産業パートナーの開発者は自らの業務成果をオープンソースプロジェクトに還元しています。GitHubリポジトリへの貢献は誰にでも開かれています。
OQTOPUSは研究プロジェクトとしての価値からも開発者を引き付けています。OQTOPUSを解説した論文「A Practical Open-Source Software Stack for a Cloud-Based Quantum Computing System」が発表されたばかりであり、さらに「Auxiliary-field quantum Monte Carlo method with quantum selected configuration interaction」という最新の研究論文の基盤にもなっています。
持続性への取り組み
多くのオープンソースプロジェクトは持続可能性の準備を怠り、既存の開発者に依存しすぎる傾向があります。しかしOQTOPUSのコミッターチームは、新たな人材を育成し、貢献者やコミッターの層がユーザーベースの多様性を反映するように努めています。
「継続的な関与と技術的信頼性」を示す経験豊富な貢献者はコードレビュアーやコミッターになることができ、さまざまな企業や研究機関を代表しています。宮永氏は「私たちは学術的責任とオープンな協働のバランスを目指しています」と述べています。チームは現在、多くの新しい組織からの関心を得て急速に成長しています。
OQTOPUSのロードマップや機能に関する意思決定はコアコントリビューターによって行われます。宮永氏はガバナンスプロセスを次のように説明します。「コアコントリビューターは隔週で会合を開き、タスクを確認し、開発を調整し、ロードマップの優先順位について議論します。プロジェクトの方向性は、所属機関に関わらず、アクティブな貢献者の合意によって決まります。」 今後の拡張計画としては、「さまざまな量子ハードウェアプラットフォームへの対応、貢献者オンボーディングの改善、量子システムソフトウェアのインターフェース標準化への参加」が挙げられています。
